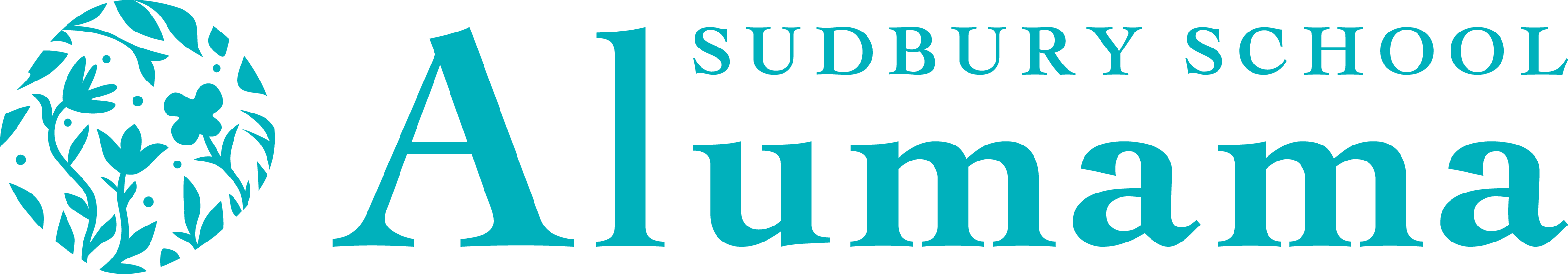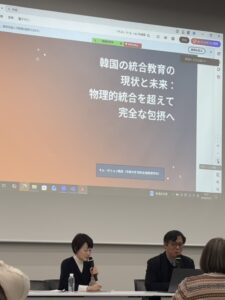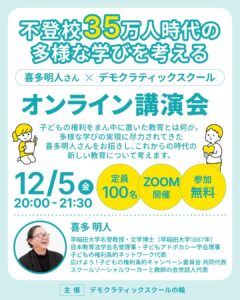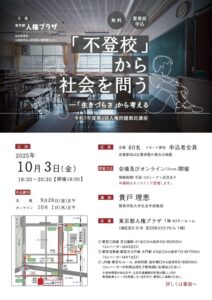今回のご講演も、やっぱり良かったです!
2月に川崎で開催されたご講演をお聞きしたばかりなのに、また感動😭
西野博之さん👉認定NPO法人フリースペースたまりば 理事長 公式サイト/facebook

簡単に内容を共有させていただきます。
これまでアルママで取り組んできたことは、「これで良かったんだ」と確信できたご講演でした✨
~不登校数・いじめ・自死などのデータや現状~
▪️増え続ける不登校
小学生 10年前の5倍
中学生 10年前の2.2倍
▪️いじめが一番多いのは…
1位 小学校2年生
2位 小学校3年生
3位 小学校1年生
小さい頃からいじめが始まっている。
▪️少子化が進んでいるのに子どもの自死は増え続け、子どもの死因原因1位が自死
これは、他の国ではみられない異常事態
▪️フランスでは、子どもが自殺したら新聞のトップページに載る
日本の悲しい現実。命の重さがまったく違う。
▪️自己肯定感が海外に比べ低い

~正しさ・過干渉・先回りの危うさ~
🔸おとなの「不安」が子どもの「自信」を奪う。親が先回りして「失敗」を未然に防止
🔸「正しい親」に見られたい
🔸「大人の善かれは、子どもの迷惑」
🔸正しさ、完璧さを求めすぎる家庭
🔸おとなが「やらせたいこと」で子どもの時間を区切っていく
🔸子どもにとって「遊ぶ」とは生きることそのもの


~非認知能力・自己肯定感・失敗できる場の重要性~
▪️AIが進み日本の労働人口の49%が人工知能など代替可能に
▪️テストでいい点を取る力は不要になる
🔸遊びがもっている力「非認知能力」を高める
人間として生きていく力を育む
▪️夢パークは「ケガと弁当、自分もち」
自分の責任で自由に遊ぶ
▪️フリースペースえん
カオスのような場所、台所が必要
ゲームOK、調理OK、テレビOK、話し合いOK
▪️安心して失敗できる環境づくりが大切


~困ったときに助けてくれる人がいればいい。まずおとなが幸せでいてください~
🔸子ども・若者が望むことは「困ったときに助けてくれる」人と場所
困ってもいないのに支援しないで!
🔸何もしてないことに緊張して、つい手出し口出ししてしまうおとなたち
🔸「なにもしない」ことの保証
🔸好奇心の芽をつまない
▪️そもそも「学校」そのものを問い直す時期にきているのではないか
150年前に富国強兵政策のもとで作り出した「学校」
▪️「学びたいことを、学びたいときに、学びたいように、学ばせてよ」
🔸子どもからおとなへのメッセージ
「まず、おとなが幸せにいてください」



「生きているだけですごい。」その言葉が、どれほど多くの子どもたちの心を救うでしょうか。
今回の講演では、不登校の現状や背景を深く知ると同時に、「子どもが安心して自分のままでいられる場所」の大切さを、改めて強く感じました。
数字の向こうには、一人ひとりの子どもたちの声があり、生きづらさがあり、願いがあります。
子どもたちは、決して何もしていないわけではなく、「自分のペースで、自分の人生を生きようとしている」のだと、教えていただきました。
まずは、子どもに何かをさせる前に、大人が変わること。
「こうあってほしい」ではなく、「そのままでいてくれてありがとう」と伝えること。
「困ったときに助けてくれる誰か」がそばにいて、「安心して何もしないでいられる時間」があること。
それが、子どもたちが自分の力で歩き出すための、はじめの一歩になるのだと思います。
私たち大人にできることは、子どもを「変える」ことではなく、子どもたちが「変わらずにいても大丈夫」と思える環境を、一緒につくっていくことなのかもしれません。